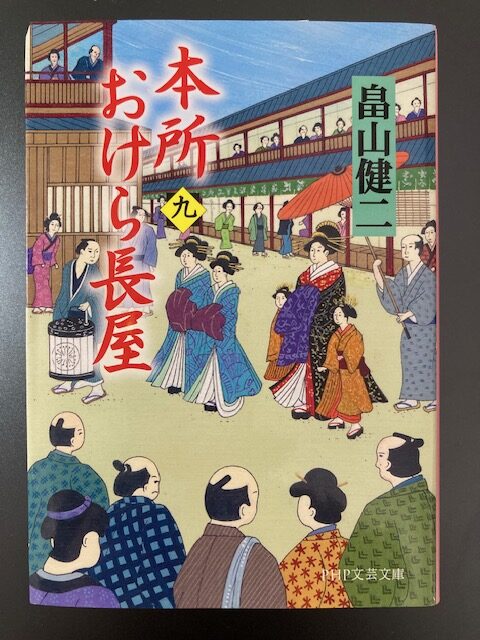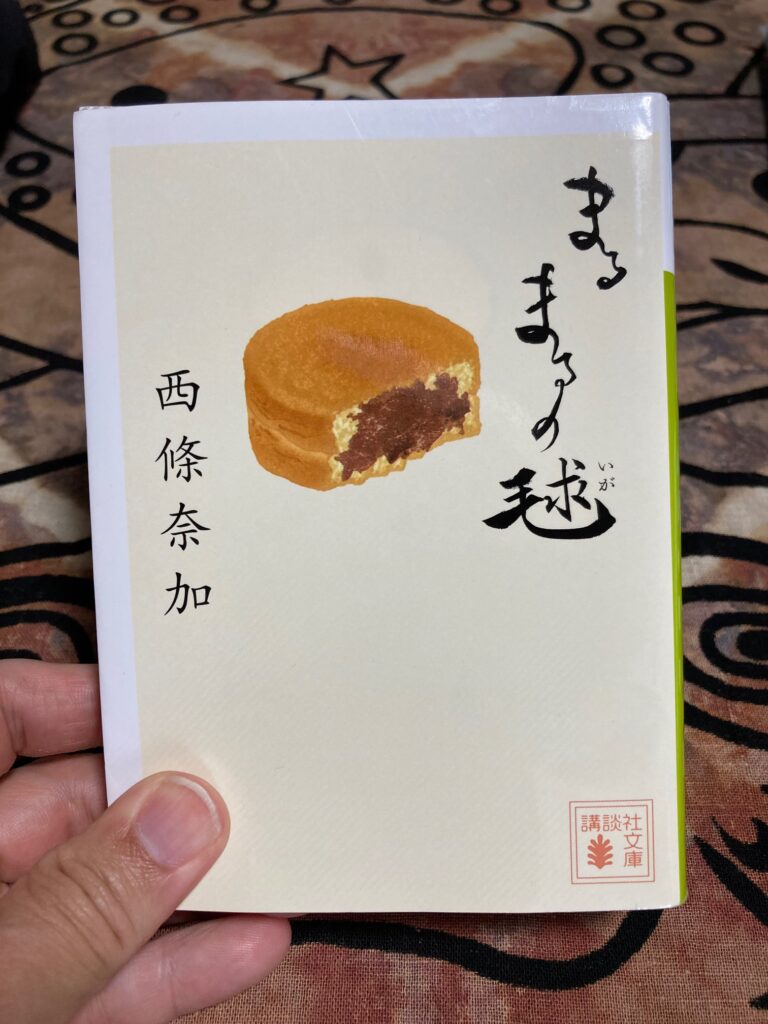畠山健二さんによる人気シリーズ『本所おけら長屋』第17巻
累計発行部数は140万部を突破している大ヒットシリーズです。
江戸下町にある貧乏長屋「おけら長屋」を舞台に、そこに暮らす個性豊かな住人たちが
巻き起こす様々な騒動を描いた人情時代小説です。
古典落語のような軽妙な語り口と、笑いあり涙あり恋愛の物語が魅力です。
時代小説のジャンルではありますが「恋愛小説」ともいえるおもしろい小説です。

◆あらすじ
物語の舞台は、江戸の大川(隅田川)に注ぐ竪川のほとりにある、九尺二間の貧乏長屋
「おけら長屋」です。米屋の奉公人・万造、酒屋の奉公人・松吉の「万松」コンビ、左官の八五郎
とお里夫婦、訳あり後家のお染、浪人の島田鉄斎といった、一癖も二癖もある住人たちが、貧しい
ながらも人情深く助け合って暮らしています。
『本所おけら長屋(十七)』では、各巻で設定される「裏テーマ」として「家族のつながり」に
スポットが当てられています。今回の巻には四つのストーリーが収録されており、夫と妻、
親と子など、身内同士の心と心の葛藤や触れ合いが描かれています。
具体的なエピソードとしては、剣の達人である浪人・鉄斎が大店の後家に見初められて婿入りする
という噂が長屋に広がる話や、久蔵とお梅の子である亀吉が友達に怪我をさせてしまい、長屋全体
を巻き込む騒動がお白洲にまで発展する話などはおすすめミステリーとしても楽しめる一遍です。
これらの物語を通して、江戸の人々が織りなす笑いと涙、そして現代にも通じる家族の絆について、
楽しみながら考えさせられる一冊となっています。
◆おすすめする人はこんな人
『本所おけら長屋(十七)』、そしてこのシリーズは、以下のような方々におすすめです。
・時代小説初心者の方:時代小説に馴染みがない方でも、登場人物の会話を中心に構成された、
テンポの良い文章で読み進めやすいのが特徴です。専門的な描写や時代背景の補足説明が
可能な限り排除されているため、気軽に楽しめます。
・古典落語や人情噺が好きな方:著者が演芸作家であるため、まるで古典落語を聞いているかの
ような、軽妙で人情味あふれる語り口が楽しめます。江戸っ子の威勢の良い会話や「地口」に
あふれており、思わず手を叩きたくなるような展開も魅力です。
・笑って泣ける物語を探している方:ユーモラスな騒動で思いっきり笑ったかと思えば、
登場人物たちの優しさや苦悩に触れてホロリとさせられたり、時には涙腺が緩んでしまう
ような感動的な場面も描かれています。
・幅広い世代で楽しめる本を探している方:小学生から高齢者まで、幅広い年代に支持されており、
子供から父母、祖父母と三世代にわたって楽しめるシリーズです。プレゼントにも適しています。
・普遍的な「家族」のテーマに触れたい方:最新刊である『十七巻』は特に「家族のつながり」が
テーマとなっており、子が母を慕う気持ち、夫婦の難しさ、父と子の心の真実、親が子供を守る
ことなど、現代にも通じる家族のあり方が描かれています。
◆『おけら長屋(十七)』の魅力 3選!
『本所おけら長屋(十七)』には、シリーズ全体の魅力に加え、本作ならではの魅力もたっぷり。
①「家族のつながり」を深く掘り下げたテーマ
今回の裏テーマは「家族のつながり」であり、収録された四つの短編すべてが、
親子や夫婦といった家族関係の葛藤や愛情に焦点を当てています。
長引くコロナ禍で家族のあり方が変化している現代において、江戸時代の人情の世界を通して、
身近な家族の関係性の大切さをきっと思い出すことでしょう。
②お馴染みの住人たちが巻き起こす笑いと涙の「珍騒動」は必見!
おけら長屋の個性的な住人たち、特に万造・松吉の「万松」コンビ、八五郎、鉄斎、お染などが、
それぞれの持ち味を発揮して物語を動かします。
鉄斎の婿入り騒動の噂に長屋中が色めき立ったり、子供の怪我を巡る長屋同士の喧嘩がお白洲に
持ち込まれたりと、一見大変な出来事も、彼らのお節介や人情によって、笑いと感動を伴う独特
の騒動へと昇華されます。この「珍騒動」こそが、おけら長屋シリーズ最大の魅力です。
③現代にも通じる人間ドラマと共感
貧しい長屋の住人たちの人間模様が描かれていますが、そこに描かれる心の内、例えば他者に
よく思われたい、一目置かれたいといった欲求や、妬み、嫉み、怒りといった感情、そしてそれら
が引き起こす「みっともない選択肢」は、現代を生きる私たちにも共感できる普遍的なものです。
しかし、おけら長屋の住人たちは、自分の弱さや欲求を互いに晒し合える素直さを持っており、
その姿は現代の私たちにとって羨ましく感じられるかもしれません。ただの古き良き人情話に
終わらず、人間の本質に迫る深みがあることも、本作の大きな魅力です。
◆各短編を徹底解説(あらすじ、解説、感想)
『本所おけら長屋(十七)』には、以下の四つの短編が収録されています。
それぞれのあらすじと解説・感想を、ご紹介します。(ネタバレ含みます)
○かえだま
三河の木綿問屋で働く作吉が、19年前に生き別れた母親・お関を探しに江戸へ来ます。
酒場「三祐」で話を聞いた八五郎たちが母親探しを手伝いますが、見つかったお関は
3年前に亡くなっていました。薩摩へ旅立つ作吉を安心させたい八五郎たちは、お関と
年齢が近いお世津に身代わりを頼んで一芝居打ちますが、結局作吉にはばれてしまいます。
しかし、一日限りの親子として心が通じ合い、角太郎(お世津の息子)が母への思いから
行動していたことも明らかになり、丸く収まります。
母親を探す息子の純粋な思いと、それに応えようとする長屋の人々の人情が胸を打ちます。
身代わりという奇抜なアイデアから起こる騒動と、その後の温かい結末が印象的です。
○はんぶん
廻船問屋「戸田屋」を切り盛りする若い後家・お多江が命を狙われ、火盗改め与力の根本伝三郎
から依頼を受けた鉄斎が用心棒として戸田屋に泊まり込みます。下手人は亡くなった戸田屋の主
の弟・鶴之助であることが判明しますが、内通者としてお多江が可愛がっていた女中のお優が弟
を脅されて協力させられていたことが明らかになります。鉄斎がお多江と協力して下手人を炙り
出す様子が、二人の仲を疑う世間の噂となり、鉄斎が大店に婿入りするという話にまで拡大します。
鉄斎に好意を寄せていたお染はお多江に会い真実を知ります。事件解決後、鉄斎はおけら長屋に戻
りますが、長屋の住人たちは鉄斎が戸田屋の親族に追い出されたと誤解したまま大喜びで迎えます。
鉄斎の剣の腕と人柄が光る話です。お多江との関係を巡る誤解が長屋で独り歩きする様子が
ユーモラスに描かれています。鉄斎が長屋を去るかもしれないという噂に、長屋の住人たち
(特に女性陣やお染)が穏やかでなくなる様子が笑えます。
○げんぺい
酒場「三祐」のお栄の伯父・晋助の一人息子である源助が、家を飛び出してから8年ぶりに現れ、
常陸国大洗から来た百姓の三平とともに、おけら長屋の松吉たちのところに転がり込んできます。
源助は家を顧みない父親(晋助)を見限っていました。二人の漫才のような掛け合いに目を付けた
松吉たちが、見世物小屋の主・田五郎に話を持ちかけると、その即興芝居が大人気となります。
芝居小屋から引き抜かれることになった二人の最後の興行で、三平がお栄の願いを叶えるために、
観客席にいた晋助を巻き込んだ一芝居を打ち、父子の仲違いが癒されます。
文字通り「笑い」に満ちた一編です。源助と三平の惚けた掛け合いが目に浮かぶようで、見世物
小屋での成功とその背景にある父子の和解という人情が描かれています。
まるで吉本新喜劇のよう、茨城弁もバリバリで笑えるポイントです。
○みなのこ
長桂寺の境内で遊んでいた久蔵とお梅の子・亀吉と、寒天長屋の忠吉が怪我をします。亀吉の手に石が
握られていたことから、忠吉の親である恒太郎とお竹、そして寒天長屋の住人は亀吉が怪我をさせたと
疑い、長屋同士の争いへと発展します。おけら長屋の面々は亀吉の無実を信じて対抗しますが、騒動は
南町奉行のお白洲にまで持ち込まれます。お白洲で久蔵は自分が調べた結果として亀吉がやったと詫び
ますが、実は別の子供が投げた石が当たったことが判明します。久蔵は真実を知りつつ、怪我をさせた
子供とその父親を庇ったのでした。奉行は久蔵の親としての深い愛情を評価し、事件は丸く収まります。
忠吉の目も大事には至りませんでした。
本作で特に感動的だと多くの読者が感じた一編です。子供を信じる親、子供を守る親の思いが深く描か
れています。亀吉は久蔵の実子ではありませんが、久蔵もおけら長屋の面々も皆で亀吉を守っており、
「みなの子」のようであるという描写が、長屋の温かい人情を象徴しています。現代の子育てにおける
悩みにも通じるテーマであり、久蔵の決断と奉行の言葉が胸にぐっときましいた。
◆まとめ
『本所おけら長屋(十七)』は、畠山健二さんの人気シリーズの第17弾として、期待を裏切らない
「笑いと涙」の人情時代小説です。特に「家族のつながり」という普遍的なテーマに焦点を当て、
現代にも通じる人間ドラマが描かれています。
古典落語のようなテンポの良い語り口と、個性豊かなおけら長屋の住人たちが巻き起こす騒動は、
読み手を飽きさせません。各短編あらすじと解説でご紹介したように、どの話もユーモアと感動が
詰まっており、読後には温かい気持ちになれることでしょう。
時代小説を普段読まない方や、幅広い世代で楽しめる本を探している方にもおすすめです。
ぜひ『本所おけら長屋(十七)』を手に取って、おけら長屋の住人たちとの交流を楽しんでみてください。
シリーズはこれからも続いており、おけら長屋の面々が次にどんな騒動を巻き起こすのか、
非常に楽しみです。