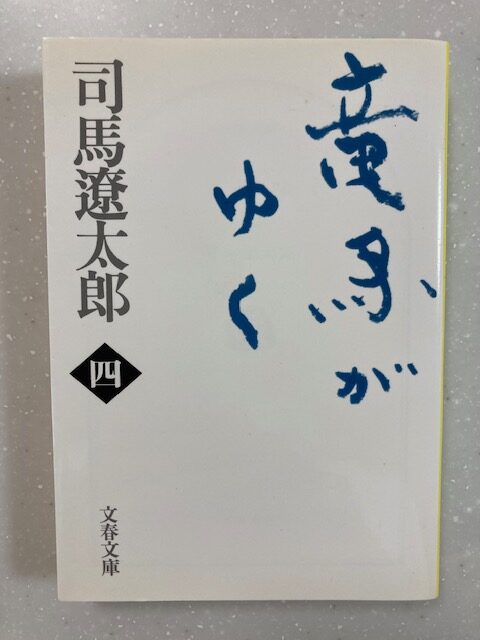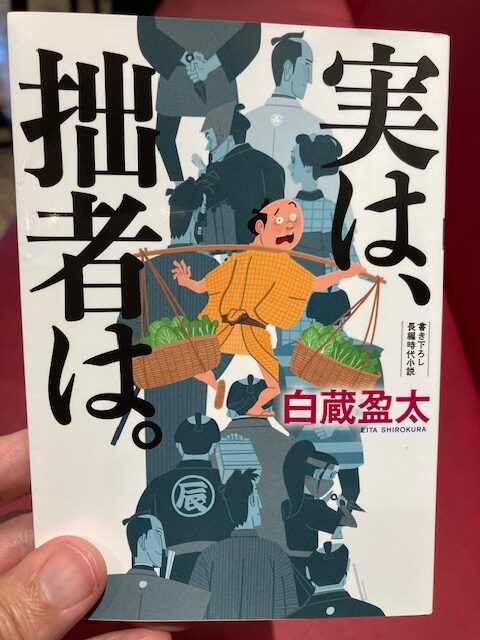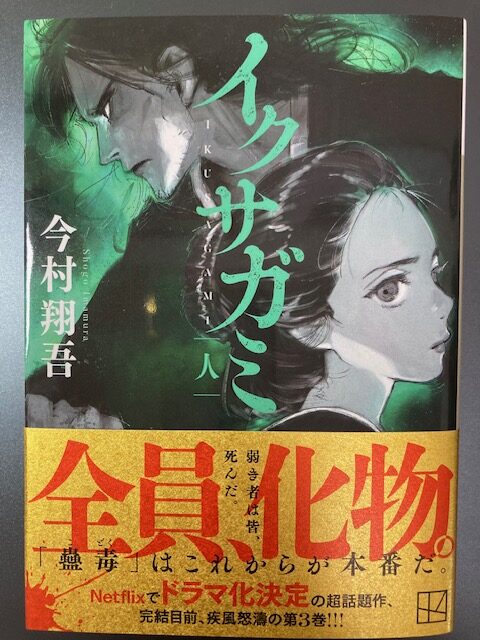『本所おけら長屋(十八)』で仕事の疲れを吹き飛ばしましょう!
50代サラリーマンが推す時代小説はこれ!

皆さん、お疲れ様です!私も普段はサラリーマンとして、日々仕事に追われています。
そんな慌ただしい毎日の中で、唯一自分だけの時間として大切にしているのが「読書」です。
特に、江戸時代の長屋を舞台にした『本所おけら長屋』シリーズは、現代社会の不安や疲れを
忘れさせてくれる、まさに私の心のオアシスとなっています。
今回ご紹介する18巻も、その期待を裏切らない、笑いと涙が詰まった傑作でした。
◆あらすじ・内容
物語の舞台は、江戸の本所にある貧乏長屋「おけら長屋」です。
ここに住むのは、金はなくても人情に厚く、お節介焼きで、時に喧嘩もするけれど、なぜか
不思議な一体感を持つ個性豊かな住人たち。彼らは日々、酒を飲んだり、博打を打ったり、
悪知恵を使って金儲けを企んだり、痩せ我慢をしたり、馬鹿をやったりと、自分勝手に
好き勝手に過ごしながらも、さまざまな騒動に首を突っ込み、時に巻き込まれていきます。
『本所おけら長屋(十八)』では、大名家の側室問題という一大事から、夫の暴力から
逃げてきた女性の離縁騒動まで、長屋の住人たちが持ち前の機転と人間力で解決に導いて
いきます。現代社会にも通じる普遍的な問題を、江戸の人々がどう向き合い、どう乗り
越えていくのか。先の読めない展開に引き込まれること間違いなしです。
◆本所おけら長屋18巻の読みどころを3つ
よみどころ①
安定の「おけら長屋らしさ」で安心感が半端ない!
畠山先生ご自身が「今回はオーソドックスに『おけら長屋』らしい話をやろうかなと」
語っているように、まさにファンが求めている「おけら長屋らしさ」が詰まった一冊です。
前巻でミステリー要素を取り入れたものの、今回は人情喜劇の王道を行くエピソードが
展開され、安心して楽しめます。馴染みの登場人物たちも増えてきて、久しぶりに活躍
するキャラクターもいるのが嬉しいポイントです。
よみどころ②
現代社会にも通じる「人間力」の答えがここにある!
現代はハラスメントなど、法律やルールが介入しなければならない問題が多いですが、
この作品では、江戸の人々が当事者間でどのように問題を解決したり、はぐらかして
生きていくかが描かれています。人間の本質は昔も今も変わっていないため、読者と
して「なるほど、こういう解決策もあるのか!」と共感し、日々の仕事や人間関係に
も応用できるような「人間力」のヒントを得られるかもしれません。
読みどころ③
「品行は悪くても品性が良い」登場人物たちの清々しさ! おけら長屋の住人たちは、
貧乏で、酒や博打に溺れる者もいますが、決して人を裏切ったり騙したりしない。
根っこの部分では「品性の良い」人たちばかりです。現代社会で外面は良いけれど
裏で何をしているか分からないような人間が増えている中で、彼らのように守るべき
ところはきちんと守る生き方は、読んでいると非常に清々しく、「こんな人たちと
付き合いたい!」**と心から思わせてくれます。
まさに、現代の私たちが飢えている「生き方」のプレゼンテーションだと感じました。
◆この本をおすすめする人
・「最近、心が疲れているな…」と感じる50代のビジネスパーソン。
・「時代小説は読んだことないけど、何か面白い本を読んでみたい」という方。
・「笑って泣ける、スカッとする話で気分転換したい」という方。
・「人とのつながりの大切さを改めて感じたい」という方。
現代社会の不安やストレスから一時的に離れ、江戸の長屋で暮らす人々の喜怒哀楽に
触れて、清々しい気持ちになりたい方に強くお勧めします。
◆各短編ごとの詳しいあらすじと感想(ネタバレあり)
第一話「あやつり」
黒石藩主・高宗に側室を迎える話が持ち上がります。高宗には17歳の正室・玉姫が
いますが、世継ぎがなく、家臣が側女を勧めます。
動揺する玉姫は、側近から「おけら長屋」の住人たちの話を聞き、
彼らが武家には思いもよらぬ手立てで問題を解決する力を
持っていることを知ります。
今回、殿様の奥さんである玉姫が初登場しました。
第二話「たけとり」
暴力亭主から逃げてきた美しい女性・お竹を、おけら長屋でかくまうことになります。
魚屋の辰次がお竹に惚れてしまう、というお決まりの失恋パターンかと思いきや、
今回はひと味違った展開が待っています。
竹取物語になぞらえた物語の進み方も、
読者をロマンティックな気分にさせてくれます。
第三話「さいころ」
おけら長屋の大家・徳兵衛とその友人たち、分別があっていつもはしっかり
しているはずの老人三人(徳兵衛、宗右衛門、聖庵堂のお満の父)が、
なんと同じ女性を好きになり一騒動起こします。
畠山先生は「ジジイになっても面白くありたい」という自身の思いを込めて
このコメディを書かれたそうで、まるで寄席の「膝代わり」
(大トリの前に出てくる笑える話)のように抱腹絶倒必至です。
第四話「きんぎん」
この巻で個人的に一番のお気に入りがこの「きんぎん」です。
棒手振りの八百屋・金太は知的障害を抱えていて、長屋の仲間からは「馬鹿金」
などと言われることもありますが、本所界隈では皆に愛される人気者。
そんな金太が、ある日白い野良犬「銀太」と出会い、絆を深めます。
しかし、その銀太が子供を襲ったという疑いがかけられ大騒動に。
長屋の面々が金太をからかいながらも、彼を「仲間で家族だ」という意識で
ピンチの時に守る姿には、思わずジーンと心が温まります。
ユーモアの中に純粋な感動が溢れる、最高の締めくくりでした。
◆著者プロフィール
畠山健二(はたけやま けんじ)先生は、1957年に東京都目黒区で生まれ、
墨田区本所で育ちました。
小説家、コラムニスト、笑芸作家として多岐にわたる活動をされています。
大学在学中にバラエティ番組『ラブアタック!』に出演され、その後は実家の
鉄鋼会社で働きながら、副業で漫才の台本を書き始めました。
1986年には、脚本・演出を担当した漫才が「第34回NHK漫才コンクール最優秀賞」を
受賞するほどの実力をお持ちです。
この経験が、『本所おけら長屋』の落語を聞いているような
軽妙なテンポの会話劇に生かされています。
2012年に『スプラッシュマンション』で小説家デビューし、
翌2013年から始まった『本所おけら長屋』シリーズがヒット作となりました。
週刊誌でのコラム連載や、ものかき塾の講師も務めるなど、精力的に活動されています。
◆まとめ
『本所おけら長屋(十八)』は、現代社会で日々奮闘する私たち
50代にとって、まさに心の栄養剤となる一冊です。
円安や戦争、未来への不安など、漠然とした不安が蔓延する現代において、
おけら長屋の人々は「笑ったり、泣いたりで忙しいですから」と語るように、
日々の喜怒哀楽を全力で楽しみ、一生懸命に生きています。
この本を読めば、彼らの溢れる人間力に触れ、きっと日々の疲れや不安も吹き飛ぶはずです。
テレビを消して、SNSも少しお休みして、『本所おけら長屋』の世界に
足を踏み入れ、登場人物たちの生き様から「人間力」のヒントを
見つけてみてはいかがでしょうか。
きっと、「明日からも頑張ろう!」という活力が湧いてくることでしょう。